本日こんなものが届きました。
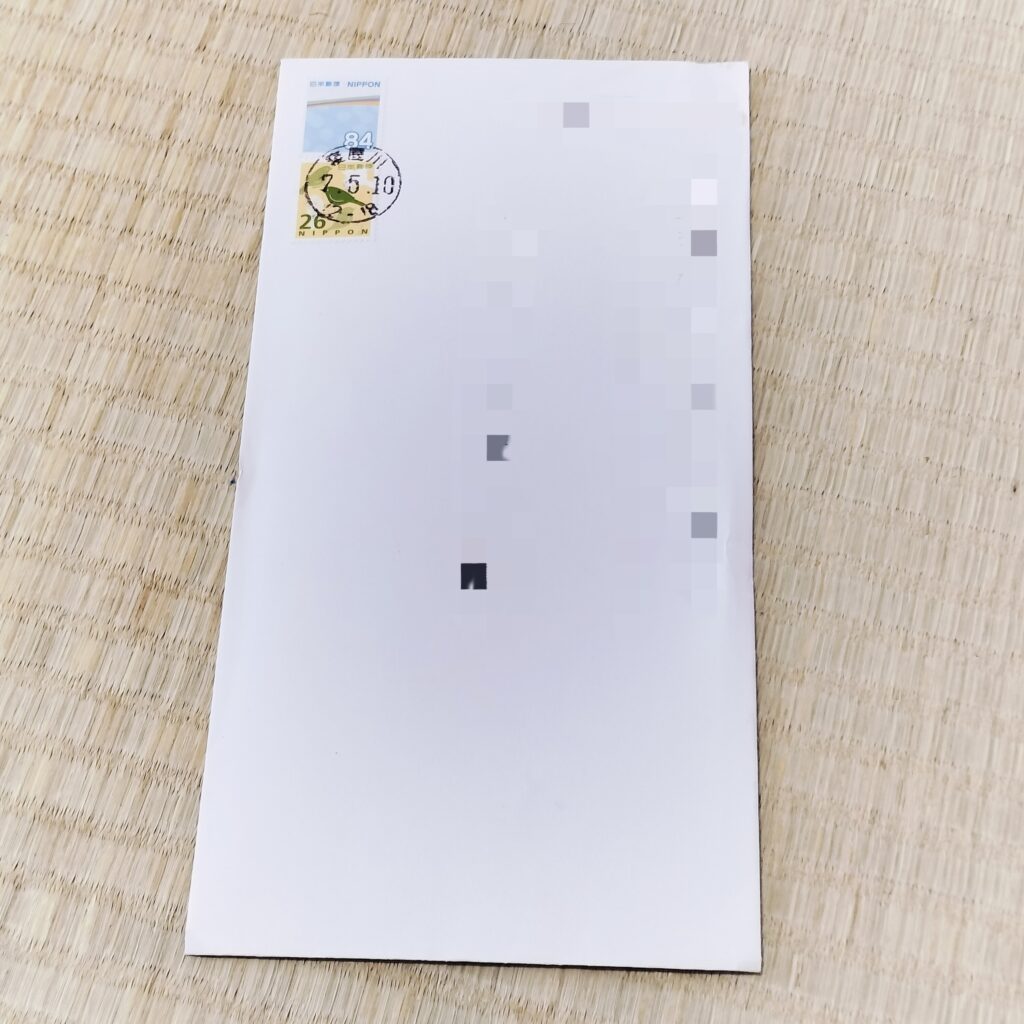
普通郵便ですね。
書留で届いた試しはないです😅
早速 開封してみましょう!


この固定の仕方は参考になります。
ベテランコレクターの技といった感じです。

届いたのは明治4年 旭日竜20銭銀貨です。
未使用級とのことです。
旭日竜20銭銀貨は、明治3〜4年という2年間だけ発行された銀貨です。
日本の貨幣製造技術が未熟だった時代ため、色々と手変わりが入っています。
- 細二
- 短年
- 横うろこ
- 曲粗葉脈
細かく見ていきましょう。

細二は、通常の「二」と比べて、線が細く、繊細な印象を与えます。

通常よりも年の文字が短くなっています。

通常の縦うろこに対して、横向きのうろこ模様が特徴です。
このバリエーションは、特定の年号や状態によって異なる価値を持つことがあります。

曲粗葉脈は、葉脈の模様が通常のものよりも粗く、曲がった形状をしているため、視覚的に異なる印象を与えます。
手変わり発生の理由
旭日竜20銭銀貨に手変わりが多い理由は、発行初期の日本の貨幣製造技術の未熟さと、製造工程の変化・改良にあります。
- 技術的未熟さ
明治初期、日本では本格的な近代硬貨の製造が始まったばかりで、プレス機や刻印の精度が十分ではありませんでした。そのため、刻印の摩耗や欠損、打刻のズレなどが頻繁に発生し、ウロコの彫りの鮮明さや文字の欠けなど、細部の違いが生まれました。 - 製造工程の変化
発行期間が短く、かつ少量生産であったため、刻印の作り直しや修正が多く行われました。例えば、明瞭うろこは初期の刻印で、後に刻印が摩耗したり修正されたことで不明瞭うろこや横うろこが生まれたと考えられます。 - エラーコインの発生
型の欠けやズレなどによるエラーコイン(文字欠けや傾打)は、検品体制が現代ほど厳密でなかったため、そのまま流通に乗ることがありました。
まとめ
旭日竜20銭銀貨には「横うろこ」「欠銭」などの手変わりや、文字欠け・傾打などのエラーコインが存在し、未だに解明、分類されていないものも多いです。
これらは、明治初期の貨幣製造技術の未熟さや、刻印の摩耗・修正、製造工程の変化によって生じたものです。
手変わりの種類などが分かってくると また 収集の幅も広がってきますね😆
以上、参考になりましたら幸いです!



コメント