こんなものが届きました。
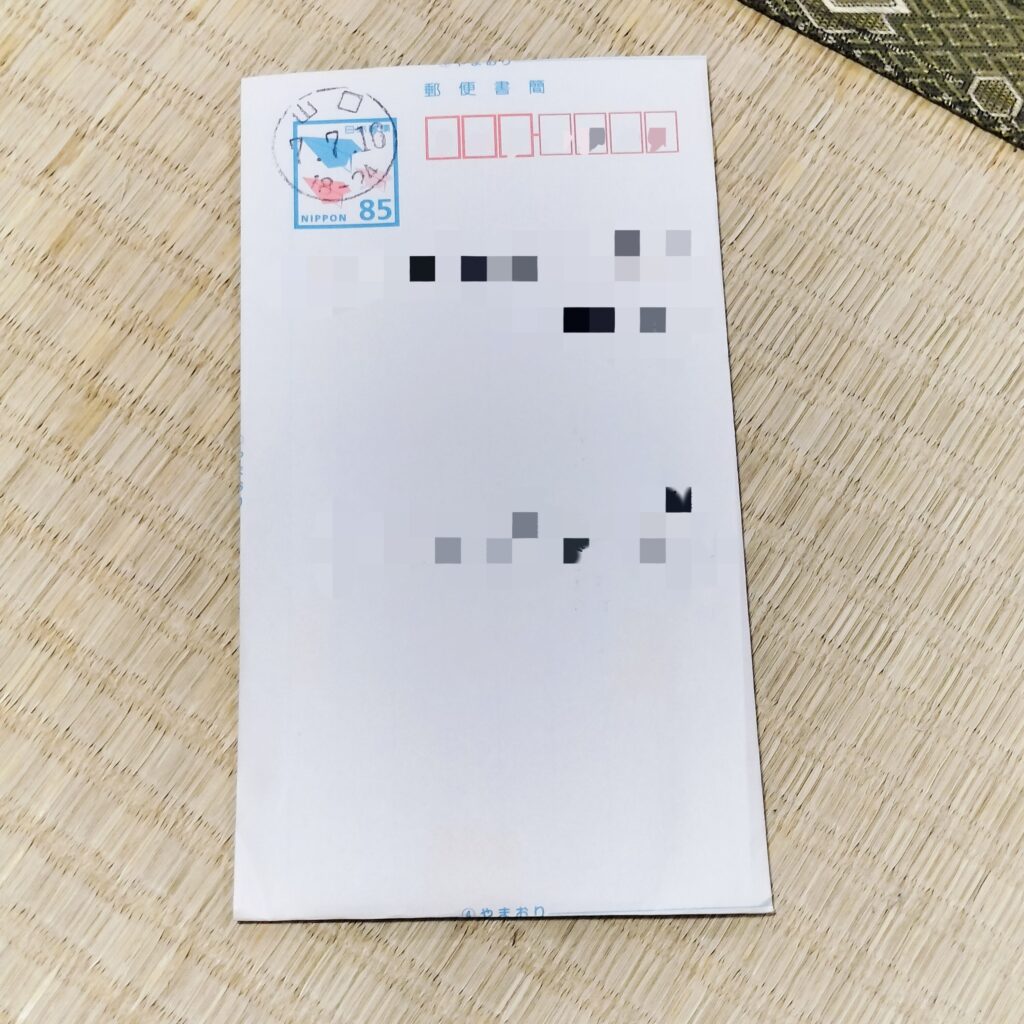
みんな大好き 普通郵便です。
早速 開封してみましょう!



中身は1916年 ロシア15コペイカ銀貨です。
これは以前から手に入れたかった15コペイカ銀貨で、ミントマークのない大阪造幣局製造の銀貨になります。
銀貨のスペックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行国 | ロシア帝国(ニコライ2世治世下) |
| 額面 | 15コペイカ |
| 発行年 | 1916年 |
| 材質 | 銀(シルバー)50%(純度0.500) |
| 重量 | 2.7g |
| 直径 | 約19.7mm |
| 厚さ | 約1.3mm |
| 形状 | 円形 |
| 縁 | ミーリング加工(ギザあり) |
| 表面デザイン | 王冠・額面・「КОПѢЕКЪ」・年月 |
| 裏面デザイン | 双頭の鷲のロシア帝国紋章 |
| ミントマーク | なし(大阪造幣局製造の特徴) |
多くの1916年ロシア銀貨にはサンクトペテルブルクなどのミントマークがありますが、「ミントマークなし」は日本の大阪造幣局で製造された証となっています。
日本の大阪造幣局でロシア銀貨が製造された理由
背景
- 1914年から第一次世界大戦が勃発し、ロシアは膨大な戦費と物資の調達が必要となりました。
- 戦争激化によりロシア国内の造幣能力が逼迫。加えてドイツなどの敵国による金属供給不足や物流の混乱で、銀貨の安定供給が困難に。
大阪造幣局による製造経緯
- ロシアは同盟国である日本に外国貨幣の製造を依頼。大阪造幣局は当時、アジア有数の高度な造幣技術と大規模生産能力を有していました。
- 日本は世界的にも数少ない「他国貨幣受託製造」が可能な国であり、英領インドやタイなど多国通貨の製造実績があります。
造られた銀貨の特徴
- 「ミントマーク」がない点が日本大阪造幣局製の特徴。
サンクトペテルブルクやエカテリンブルクなどロシア本国の造幣所だとアルファベットやキリル文字の刻印がありますが、日本製はそれがありません。 - ロシア本国造幣所の供給が追いつかない分や、海外部隊用・貿易用などの目的で日本での増産が進められました。
1916年前後の日露関係・国際情勢と歴史的経緯
日露戦争から協調へ
- 1904-1905年の日露戦争後、一時は緊迫した関係でしたが、1910年代には協調と連携の流れに変わります。
- 第一次世界大戦(WWI)ではロシアと日本は共に連合国側となり、外交・軍事面での協力体制が強化されていきました。
日露同盟の成立
- 1916年7月、日露両国は極東における勢力均衡を調整し、対ドイツ協調のために「日露同盟」(日露協約)を秘密裏に締結しました。
- この同盟により、極東・中国での独伊勢力の拡大阻止や、相互の安全保障に合意しました。
これは第一次世界大戦中の日本外交における大きな成果の一つです。
対外経済・軍事援助
- 日本はロシアに対し、武器・弾薬、軍需物資の供給を実施。
円滑な国際決済や貿易のために、ロシア貨幣(コペイカ銀貨)も日本で鋳造されることとなりました。 - 日本側にとっては、造幣受託による収益・技術力向上の機会となり、またロシア側にとっては戦時体制の資金流通確保というメリットがありました。
歴史的意義とコインの魅力
- このコインは単なる貨幣としてだけでなく、「日露協調」「国際協力」「戦時経済史」など20世紀初頭の歴史の交差点を象徴する重要な資料です。
- サンクトペテルブルクやエカテリンブルク発行のコインよりも日本大阪造幣局製・無ミントマーク品は珍重される傾向があり、コレクターの間でも高く評価されています。
まとめ
1916年のロシア15コペイカ銀貨は、大阪造幣局で鋳造された国際協力の象徴的存在です。
当時の日本とロシアは連合国として協力し、同盟関係を結び、経済的、軍事的にも深い結びつきを築きました。
この銀貨は、戦時の国際情勢や異文化交流、技術のグローバル化を語るうえで貴重な証拠となっています。
以上、参考になりましたら幸いです!



コメント