日本の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条では、同一の貨幣(硬貨)に関して、その使用は「額面価格の20倍まで」を限度として法定通貨として通用すると定められています。
つまり、例えば100円硬貨であれば、20枚(合計2,000円)までが法的に支払いに使える限度となり、それを超えての支払いは受け取り側に拒否される可能性があります。
ただしこれは同じ額面硬貨の枚数制限であって、異なる額面の硬貨を組み合わせればそれぞれ20枚ずつ使用可能です。
たとえば100円玉20枚と50円玉20枚は別々に通用します。
この法律は通常の流通硬貨だけでなく、100円銀貨(例えば昭和34~41年発行のもの)、旧ニッケル製の50円玉(穴なし5円玉)、そして国会議事堂が描かれた穴なし5円玉などの旧貨幣や、記念硬貨にも適用されます。

記念硬貨も法定通貨として有効であり、この使用限度の規定に含まれます。
ただし、これらの貨幣は流通量や使用機会が少ないため、実際には取引での利用や店舗での受け取りが難しい場合もありますが、法律上は有効な通貨です。
法律の内容のわかりやすい説明
日本の現行の流通貨幣は1円、5円、10円、50円、100円、500円の6種類の硬貨があります。
このうち、同じ種類の硬貨は一度に20枚までしか支払いに使えません。
これが「額面価格の20倍まで」通用するという意味です。
たとえば10円硬貨なら20枚で200円まで、500円玉なら20枚で合計1万円までが限度です。
これは店舗の「硬貨は20枚まで」という表示の根拠にもなっています。
一方、紙幣(お札)は枚数に制限がなく、いくらでも使えます。
硬貨は大量に使われると不都合が生じやすいため、このような制約が法律で設けられているのです。
一般人が気をつけること
- 支払い時に同一硬貨が20枚を超える場合、店舗側は受け取りを拒否できる権利が法律で認められています。
- 古い硬貨や記念硬貨も法定通貨ですが、使い慣れていない場合は店舗や自動販売機で使えないこともあるため、注意が必要です。
- 特に旧100円銀貨、旧ニッケル50円玉、穴なし5円玉などは受け取り側が知らないこともあり、使いにくいことがあります。
- 記念コインは価値がある場合が多く、売買時には法律上の支払いだけでなく、コレクター市場での価値も考慮しましょう。

現行貨幣外の特殊硬貨の法律適用
- 旧100円銀貨(昭和34年~41年発行)は流通しており、法定通貨としてその使用及び20枚までの制限が適用されます。
- 旧ニッケル製の50円玉(穴なしタイプ)も現行と同じく有効な貨幣です。
今も法定通貨として使えますが、流通は少なくなっています。 - 国会議事堂の描かれた穴なし5円玉も現状は有効な法貨として扱われます。
- 記念硬貨は閣議決定に基づき発行されており、これらも同様に法定通貨としての効力を持ちます。
- ただし、これらも日常的な流通に適しているわけではありません。
以上、同一硬貨20枚までの使用制限は通常硬貨に限らず、旧硬貨や記念硬貨にも及ぶことを理解し、使用時には店舗ルールや相手の理解を考慮することが大切です。

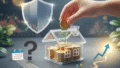

コメント