縁があって色々集まった 大型5銭白銅貨です。
YouTubeで大型5銭白銅貨のショート動画も作成したのでよろしければ観てください😊
チャンネル登録もよろしくお願いします🙇
大正時代に4年間だけ発行された大型5銭白銅貨は、1917年(大正6年)から1920年(大正9年)にかけて製造された日本の補助通貨の一つです。
この貨幣は当時の社会経済状況や貨幣制度の変化の中で誕生し、短命であったことが特徴です。
発行の背景
明治時代の終盤から大正時代にかけて、当時の日本では銀貨が主要な少額硬貨でしたが、小さくて使いにくい銀貨の代替として、白銅(銅75%、ニッケル25%)を素材にした大型の5銭貨が求められていました。
特に第一次世界大戦中の銀相場の高騰により、銀貨の鋳造が難しくなり、代替硬貨が必要とされた時代背景があります。
また、従来の「菊五銭白銅貨」(明治22年から発行)は偽造が多発し識別が困難だったため、より偽造防止を強化する目的で、1917年に「大型五銭白銅貨」が新たに発行されることとなりました。
この新しい貨幣は有孔貨幣(中央に穴をあけたコイン)として、日本の近代貨幣史で初めて採用された意匠であり、穴の開け方や表面のデザインで偽造対策を図りました。
特徴とデザイン
大型5銭白銅貨は径20.6mm、重さ4.28gで、素材は白銅が使われています。
表面には「五銭」と桐の紋章があり、裏面には青海波模様と八稜鏡(はちりょうきょう)が配されています。
穴あきの仕様により、視覚的に他の貨幣と区別しやすく、また材質の節約も図られました。
短期間発行の理由
大型五銭白銅貨は短命に終わった理由は複数あります。
まず図案自体は偽造防止を目的に設計されたものの、十銭白銅貨など当時の他の貨幣と類似し、混同されやすいという欠点がありました。
また、発行当時の物価変動や貨幣流通の変化により、1920年(大正9年)にサイズを小さくし、より流通しやすい「小型五銭白銅貨」が採用されたことで大型5銭白銅貨は終了しました。
さらに、当時の経済状況や貨幣政策の変遷も短期間での切り替えに影響しています。
現在の市場価値
今日では大型5銭白銅貨は発行枚数が約8300万枚とそれほど多くなかったこと、かつ短期間の発行であることから希少性が評価されています。
流通良好品から未使用品まで、年号や状態によって価格差はあるものの、一般的には数千円から一万円台程度で取引されることが多いです。
特に美品や希少な年銘の個体はコレクターから高い関心を集め、高値取引になることもあります。
まとめ
- 発行期間は1917年(大正6年)から1920年(大正9年)の4年間
- 素材は銅75%、ニッケル25%の白銅で、初めての有孔(穴あき)貨幣
- 当時の銀貨の偽造問題対策および物価・貨幣流通の変化に対応するため短期間で発行・廃止
- 市場価値は希少性により一定のコレクター価値があるが、流通品は比較的手頃価格
大型5銭白銅貨は、日本の近代貨幣史の変遷が色濃く反映された興味深い貨幣であり、短期間の発行ながら現在でも古銭ファンから注目されています。
以上、参考になりましたら幸いです!


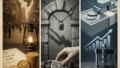
コメント